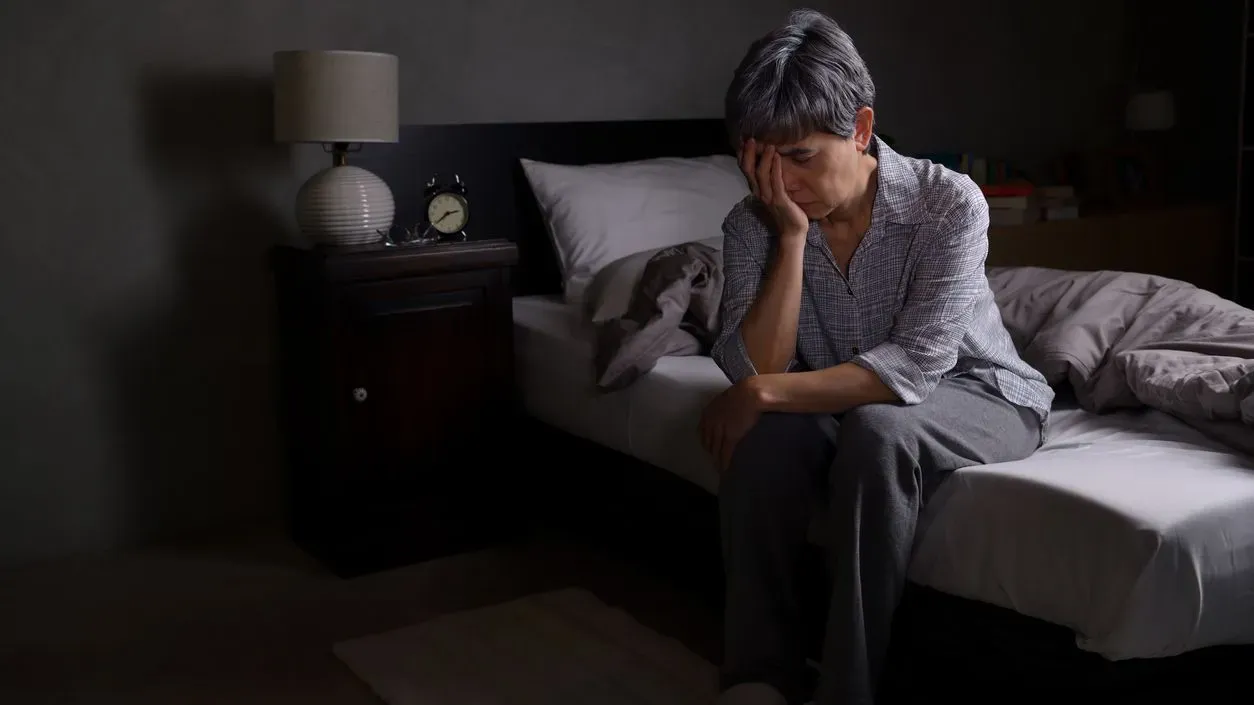「何となく最近、もの忘れが増えた気がする」「昔より、覚えられないことが増えてきた」このように感じることはありませんか?
もの忘れのすべてが病気というわけではありませんが、なかには注意が必要なものもあります。
この記事では、記憶力が最近気になっている方に向けて、記憶の仕組みと脳の関係について具体的な例も交えて解説します。日々の暮らしに役立つヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。
脳が記憶する仕組みとは?記憶のプロセスを解説
記憶は、記銘、保持、想起というプロセスから成り立っています1。日常生活で使う場面に当てはめながら、これらのプロセスについて知りましょう。
記銘
記銘は、目や耳から入ってきた新しい情報を脳に取り込み、ものを覚える段階です。記憶を情報処理的な観点からみた場合、記銘するプロセスをコード化と呼ぶこともあります1。
脳をコンピューターに見立てたとき、情報を入力する段階が記銘にあたるともいえるでしょう。日常的には、人やものの名前を覚えることなどの場面で使います。
保持
保持は、入ってきた情報を脳の中で保管する過程です。情報処理的な観点からは、脳に情報を貯蔵しておくことともいえます1。
記憶の保持は覚えていられる時間の長さによって区切られ、以下のような記憶の種類があります。
即時記憶
即時記憶は、刺激や出来事の記銘後すぐに思い出させる、干渉をはさまないような記憶です。誰かが口にした数字を、すぐにそのまま言い返すといった場面で使われます2。
電話中に相手から聞いた電話番号を確認するために復唱することなどが即時記憶の一例です。
近時記憶
近時記憶は数分〜数時間、あるいは数日ほど覚えていられる記憶です。言葉を覚えてもらって5分後にまだ覚えているかどうかを確認するテストなどは、この近時記憶の働きを調べるものです2。
献立を考えるときに昨日何を食べたか?を考えることなどが、生活のなかでよく使う近時記憶の1つです。
遠隔記憶
遠隔記憶は、数年前や何十年も前に起こった事柄に関する記憶です。学生時代のエピソードや旅行、結婚にまつわる思い出など、長く心に残っている記憶が遠隔記憶にあたります2。
想起
想起は覚えていることを思い出すことです。脳から必要な情報を探索する過程でもあります1。友人に会って名前を呼ぶときや、昔の旅行の写真を見て当時の出来事を語るときなどに働くプロセスです。
記憶のプロセスに問題があるときに生じる記憶障害のメカニズム
これらの記憶の流れがどこかでつまずくと、覚えられない・思い出せない状態になります。さらに記憶はその内容によって、エピソード記憶・意味記憶・手続き記憶など、さまざまな種類に分類されます2。そのなかで日常生活に直結しやすいのがエピソード記憶でしょう。
これは「昨日の夕食はどこで誰と何を食べたか」といった、自分が経験した出来事の記憶にまつわる記憶です2。
記憶障害というと、このエピソード記憶がうまくできない状態を指すことが一般的です2。エピソード記憶が作られるときには、脳でも海馬(かいば)を含む側頭葉が大きな役割を果たしています3。
そのため、海馬をはじめとする側頭葉の機能がそこなわれると、記憶の抜けやすさが目立ってきます。これらの原因には、アルツハイマー型認知症4などの認知症、頭のケガによる脳の損傷3などがあります。
記憶障害の分類と暮らしの困りごと
記憶障害は記銘、保持、想起のどの段階でも起こります。ここでは、タイプ別に日常でみられる記憶障害の様子をみていきましょう。
体験や行為を記憶できない
自分がした体験や行為にまつわる記憶が、一部またはすべてが抜けるタイプの記憶障害で、健忘と言われています。主に次のような様子がみられます。
- ・ 人の名前や話した内容が思い出せない
・ 旅行などの体験の記憶を思い出せない
・ 同じ話を何度もする
・ 「はじめまして」と挨拶したところ「この前会いましたよ」と言われた
加齢によるもの忘れでも生じることはありますが5、以下のような症状の場合、それ以外の要因が関わっている可能性があります。このような場合は、医療機関への相談を検討してもよいでしょう5。
- ・ 急にもの忘れが悪化する
・ ヒントがあっても答えられない
・ そもそも本人にもの忘れの自覚がない
・ 体験したことそのものを忘れる
知識・情報を記憶できない
多くの人が常識として知っている知識などが、すっぽりと抜け落ちてしまうタイプの記憶障害もあります。例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- ・ペンギンという言葉は、丸みを帯びた姿の飛べない鳥を表すことなどがわからない6
・地図記号やトイレなどを示すサインがわからない6
・新宿は東京都にあるということがわからない6
こうした症状は、意味記憶障害の可能性があります。加齢のほか、認知症を引き起こす病気の1つである前頭側頭葉変性症や、ヘルペス脳炎、脳の損傷など、側頭葉が傷つけられるような病気が原因となることもあります6。
誤りや事実でないことを正しいこと・事実と思い込んでしまう
記憶は歪められてしまうこともあります。
- ・ 起こっていない出来事や事柄を覚えている
・ 起こった出来事を、実際とは全く違うように覚えている
このような記憶は、虚偽記憶(きょぎきおく)とも呼ばれます7。
原因はまだはっきりとはわかっていませんが、加齢などに伴って脳の前頭葉機能が低下することとも関連があるのではないか、と考えられています7。
見聞きしたこと・考えたことが瞬時に記憶から消え去る
見たそばから忘れてしまう、しようとしていたことを忘れてしまうタイプです。
- ・メモを見て入力しようとしたのに別のことをして忘れる
・聞いたことが数秒で抜け落ちる
目や耳から入ってきた情報は、いったん即時記憶としてキープされます。しかし、脳が他のことに注意を向けると、この即時記憶はすぐに消えてしまいます8。
そのため、すぐに忘れてしまうからといって、すべてが病気というわけではありません。
また、即時記憶には覚えていられる量にも限りがあります。一般的には、健康な人でも一度に覚えられるのは7つ前後までといわれています。それを超えると、古い情報から順に忘れてしまうことが多いのです8。
即時記憶の障害は、脳に損傷を負ってしまった方の障害の1つとして現れることもあります。しかし、即時記憶障害だけが現れる方はまれとされています8。
忘れてしまったり思い出せないことへの対策方法
最近、もの忘れが増えたと自覚して、どうすべきかとお困りの方もいらっしゃるでしょう。そのようなときには、以下のような対策を暮らしに取り入れてみてはいかがでしょうか。
スマートフォンに予定を登録してアラームをセットする
うっかり忘れへの対策や、記憶障害がある方に役立つものの1つに、スマートフォンのアラーム機能があります9。
予定だけでなく、服薬やゴミ出しなど、日常のルーチンもセットしておくとより安心できるでしょう。
忘れ物防止タグを活用する
鍵や財布など、よく置き忘れてしまいがちなものには、忘れ物防止タグを装着するとよいでしょう。スマホなどと連動し、一定の距離を離れると通知してくれるタイプだとより便利ですね。
探し物に費やす時間を減らせるだけでなく、忘れても何とかなる、という安心感が得られるのもメリットといえます。
チェックリストで順番を見える化する
行動の順序をチェックリストにして、常に目に見える場所に貼っておくというのも良いでしょう10。一つ一つの工程を思い出す必要が減るため、何かを忘れるといった失敗を減らすことにも役立ちます。
音声によるリマインド
スケジュール管理の助けとして、ICレコーダーなどを活用するのもよいでしょう10。時間ごとの指示をあらかじめ録音し、タイマー機能で決まった時間内に音声出力することで、大切な用事を思い出すことができますね。
まとめ|記憶の仕組みと脳の関係:なぜ忘れる?どうすれば覚えられる?
もの忘れは誰にでもありますが、ちょっとした工夫で日常生活をより快適にすることができます。
小さな工夫が、毎日の安心感や自信につながります。無理のない範囲で、自分らしい工夫を取り入れて、いきいきとした毎日を過ごしていきましょう。