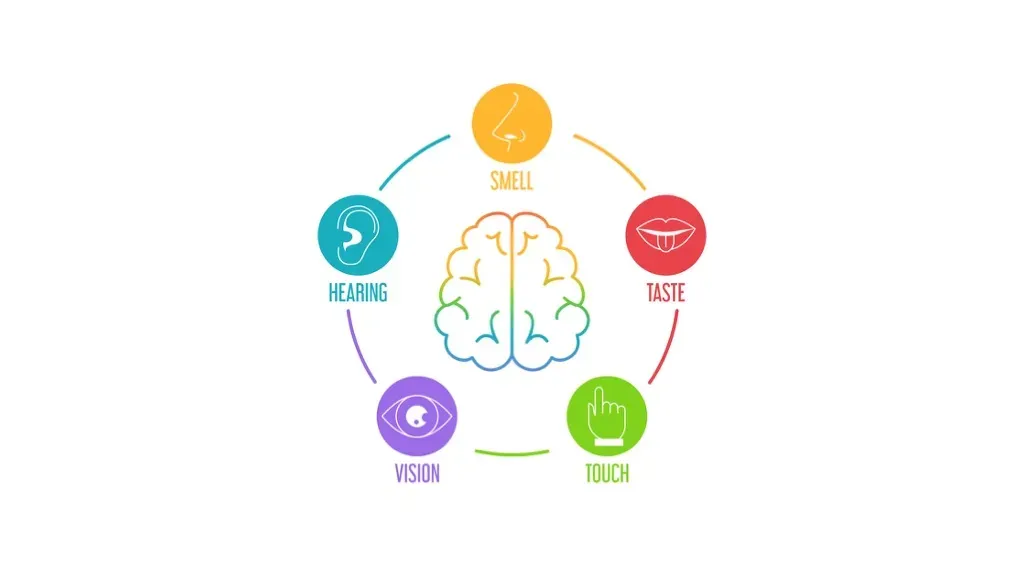「神経科学」に真剣に取り組む高校生たちがいます。
中高生が神経科学に興味を持つきっかけを提供することを目的として、広尾学園高等学校に通う小澤美咲さんがIYNA Japan(International Youth Neuroscience Association 日本支部)を作り、日々活動しています。
どのような背景があり、高校生の小澤さんが神経科学のコミュニティを作ることになったのか。団体設立の経緯から普段の活動、さらに小澤さんご自身が神経科学に没頭するきっかけや現在の取り組みについて、お話を伺いました。
IYNA Japanの活動について

最初に、IYNA Japanの団体概要、活動の目的を簡単に教えていただけますか。
IYNA Japanは、International Youth Neuroscience Association(IYNA)という中高生の国際神経科学団体の日本支部です。
母体のIYNAは2016年に国際脳科学オリンピックの経験者が立ち上げ、現在は4,000人以上のメンバーと126国以上の支部がある大きな団体ですが、日本には昨年まで支部がありませんでした。
そこで、中高生が神経科学に興味を持つきっかけを提供することを目的に、私が2024年10月にIYNA Japanを立ち上げ、コミュニティ作り・教育活動・発信活動などを行っています。

現在のIYNA Japanの活動体制やメンバー数について教えてください。
Discordで日常的に交流しているメンバーは現在110人です。講演会やイベントに参加してくれた方を含めると、さらに多くなると思います。
その中で、運営に直接関わっているメンバーは18名です。この18名のメンバーが中心となって、勉強会やイベントの企画、SNSやnoteでの情報発信などを担っています。

運営メンバーは具体的にどのような班に分かれて活動されているんですか?
班はいくつかあります。例えば、Instagramで神経科学に関する雑学や最新の研究成果を投稿するSNS班、外部イベントの宣伝や企画調整を行う広報班、学会でのポスター発表や展示会でのアンケート調査などを実施する研究班、研究室見学や講演会を企画するイベント班、脳科学オリンピック形式の模試を作成するテスト班、あとは財務班もいます。
これらの班がそれぞれ活動し、2週間に1度の定例会で進捗を共有しています。

研究班では学会発表や展示会もされているんですよね。
はい。今年の2月にはAPPW2025(第130回日本解剖学会・第102回日本生理学会・第98回日本薬理学会 合同大会)という学会でIYNAの活動のポスター発表を行いました。
また、3月には渋谷スクランブルスクエアでの展示にも参加しました。QWS(キューズ)チャレンジというものに採択されて、その活動の一環として渋谷スクランブルスクエアで展示をしたんです。
そこでは来場者の方々に「脳科学と聞いて何を思い浮かべますか?」といったクイズやアンケートを取りました。そのデータはまだ公開していませんが、研究班でデータ化して、どこかで発表できたらと思っています。
APPW2025でのポスター発表

脳科学オリンピックへの貢献も大きいと伺いましたが、具体的にどのような取り組みをされているんですか?
脳科学オリンピックの参加者を増やしたいという思いが強くあります。脳科学オリンピックでは、The Brain Facts Bookという公式テキストから問題が出題されるのですが、出題が英語なんです。それが一番のハードルになっていると思い、対策として輪読会を実施しています。テキストの18章を各章1人ずつ担当し、英語で学んだことを日本語で発表し合うんです。
その結果、今年の脳科学オリンピックの本選進出者10人中6人がIYNA Japanのメンバーで、さらに去年は8割だった本選への出場基準点数が、今年は9割に上がりました。平均点も本選のベンチマークも上がっていて、何かしら貢献できたかなと思っています。

学校の試験や部活などもあると思いますが、高校生活との両立は大変ではないですか?
隙間時間に活動しようというスタンスで、正直、メンバーに義務感を持って活動をしてほしくないと思っています。
定例の会議でも、期末試験や中間試験が近い人がいないか聞いたり、難しい時は遠慮なく断ってほしいと伝えています。みんなも気軽に断ってくれるので、断りやすい空気はできているかなと。
インスタ投稿も以前は毎日やっていましたが、今は週1回など、できる範囲でやっています。無理をして神経科学を嫌いになってほしくないので、高校生の間は楽しめる気持ちを大切にしています。